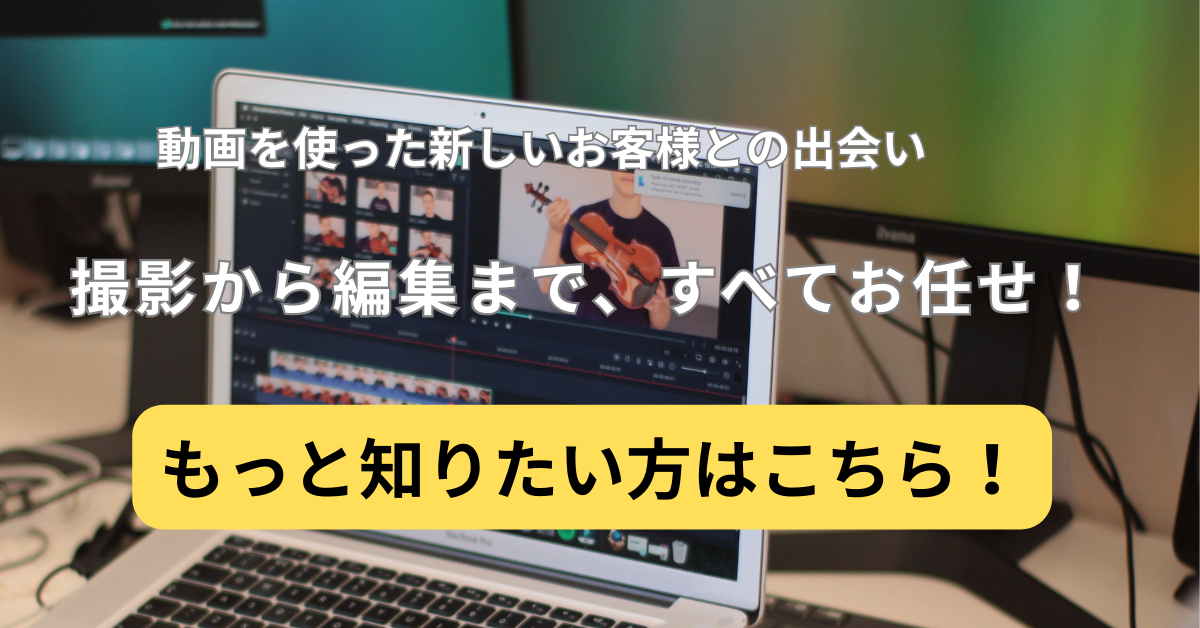練馬区のウェブ議員新聞から
- すべて
- 練馬区議ウェブ議員新聞から
-
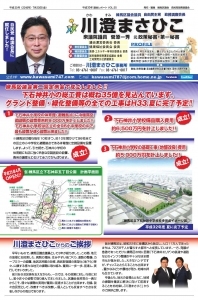
下石神井小学校について 2018年 7月 18日
まちづくり
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2018-11-8
下石神井小の総工費は概ね億を見込んでいます。 グランド整備・緑化整備等の全ての工事は夏に完了予定 !! ①下石神井小学校の体育館(避難拠点)に冷暖房空調設備の設置費用約万を計上しました!! 下石神井小学校は区立の全小中学校の中で 最も設置が速く設置出来ました!! ※練馬区は概ね毎年校ずつ、約年間かけて校全ての区立の小中学校に避難拠点である体育館に空調設備を設置します。 よって、引き続き、石神井小学校の体育館にも区に強く早急な空調施設の設置、 費用の議案化にむけて全力でがんばります ②下石神井小学校備品購入費用 約万円を計上しました!! ③下石神井小学校の基礎工事(地盤改良)費用 約万円を計上しました!! ★平成年月!! 仮)練馬区立下石神井五丁目公園 外周部(住宅側) ・中低木をベースに緩衝緑地を設けます。 ・宅地との境界には高さのフェンスを設けます。 運動ゾーン ・高齢者が使用可能な健康器具を配置します。 遊戯ゾーン(南側) ・~才(児童)主体として遊べる遊具を配置します。 外周部(道路側) ・緩衝緑地を設け、道路から公園から見通せるよう整備します。 ・道路との境界には高さ程度のメッシュフェンスを設けます。 遊戯ゾーン(南側) ・~才(幼児)を主体として遊べる遊具を配置します。 草地(ニッケイの根回し工事について ) ニッケイの木については公園 整備工事に伴い移植をする予定ですが、移植後の生育をよくするための処置(=根回し)を以下の期 間で行います。 ※本整備工事とは別に 先行して行います。 平成工事期間:年3月上旬~ 平成年3下旬(予定) 川澄まさひこ 議会レポートより抜粋
-

川澄まさひこからのご挨拶 2018年 7月 18日
その他
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2018-11-8
早いもので、 練馬区議会議員として年が経ちました。 この間、地元の皆様にお約束した、 病院の増床、住みやすい街づくり、 道路の整備、カ ーブミラーの設置、地区区民館の改修、 西武新宿線の高架化(地下化)等々、 山積する様々な地元の課題に取り組み、 着実に一歩一歩、前進し、実行してまいりました。 前川あきお区長を支えながらも、 一方では、その政策に対し、行政に対し、 是々非々の姿勢で取り組んでまいりました。 区議会自民党の一員だからこそ、 様々な課題の実現が着実に前進することが出来ます。 勿論、我々自民党として、改善すべきは改善し、 個人としても反省すべき点は反省しながらの毎日であります。 我が練馬区は、昭和22年に板橋区から独立し、 人口11万人であったまちは、 72万8千人が暮らす大都市へと成長しています。 一方、発展が急激であっただけに 練馬区の特に西側(下石神井エリア)の鉄道や道路などの インフラ整備が不十分なまま都市化が進みました。 大きなハンデですが、チャンスととらえることも出来ます 。 豊かなみどりや農地が残り、地域の絆も生きています。 今後とも、地元の皆様とともに、 地域 の課題を着実に解決に向けて前進することをお約束し 「川澄まさひこ」から のご挨拶と致します。 「平成年議会レポートv」 より ★かわすみ雅彦 プロフィール://--///
-

上野ひろみ 一般質問(要旨)その2 2015年 1月 23日
定例会
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2018-11-7
<鉄道駅のバリアフリー化について> 【質問3】 「地下鉄赤塚駅」をはじめとした、区内の鉄道駅の更なるバリアフリー化について、現在の進捗状況と、今後の取り組みについてお伺い致します。 また、ハード面の整備と合わせて、障害者等に配慮した情報提供や、思いやりの心の醸成など、ソフト面の取り組みの推進も不可欠であると考えます。鉄道事業者と連携した、これからの取り組みについても、強く要望致しますが、区のご所見をお聞かせ下さい。 【⇒3答弁】 利用者の実態調査やアンケートを実施し、バリアフリー施設に関する改善点などを整理したところです。地下鉄赤塚駅において、練馬区側の出入口について、エレベータ設置の計画を進めています。現在地域の方の協力を得て、現地調査を進め、来年度の工事着手に向けて、関係者との詰めの調整を行っています。 <自転車駐車場の整備について> 【質問4-①】 午後の時間帯になると、駅周辺の商店街での買い物客等で、午前の約2倍から4倍の放置自転車が発生している現状もあることから、更なる取り組みの強化が必要であると考えますが、区のご所見をお伺い致します。 【⇒4-①答弁】 地域の協議会などと協働し、撤去時間の拡大や、店舗等の敷地からはみ出した自転車の対策など、午後の放置対策をさらに進める。 【質問4-②】 本来「ふれあいの径」は公園であり、駐輪機が大量に設置されるのは好ましくありません。私は以前から提案をさせて頂いております、光が丘駅周辺には恒久的な自転車駐車場の整備が必要であると、強く要望致しますがいかがでしょうか。区のご所見をお聞かせ下さい。 【⇒-②答弁】 必要な規模を精査して、引き続き確保が図れるよう都と協議する。 【質問4-③】 光が丘駅周辺で最大の収容台数2220台を持つ、光が丘自転車駐車を撤去しなければならないという状況からも、再びこの地域に放置自転車が増大してしまう恐れがある。都道や駅前ロータリーの地下を活用した、本格的で機能的な最新鋭の自転車駐車場の整備が必要出ると考えますがいかがでしょうか。 【⇒4-③答弁】 関係機関の協力を得ながら、様々な方策を検討する。 <「田柄川緑道」の再整備について> 【質問5-①】 平成19年の初質問から、これまでも幾度となく、この課題についてお伺いして参りました。その結果、「道路・河川の緑化、『みどりの基本計画』に基づき、水とみどりのネットワークづくりの促進と周辺環境向上のため、田柄川緑道の再整備を進めます。」と、長期計画に位置づけ整備を行う水辺拠点候補地として頂きました。この事については、大変評価させて頂いております。 しかしながら、その後状況は一転し、近年の度重なる時間降水量100ミリを超す、「ゲリラ豪雨」と称される局地的な大雨の被害により、いわゆる田柄川幹線流域もその影響を受け、まずは、緑道の地下を流れる下水道の冠水対策を最優先課題として取り組むことが、必要不可欠な状況となりました。 前志村区長も当地域の事態を重く受けとめて頂き、すぐさま、区長みずからが、都の下水道局長に面会して頂き、豪雨対策に関する要請を行って下さいました。その後、合わせて我が自民党の、練馬区選出の東京都議会議員の働きかけと共に、また被害に遭った町会、あるいは商店街等々を中心とした、3462名にのぼる署名と陳情書を、地元の村上議長と私と代表し、区長にもご同行して頂き、下水道局長に提出をさせて頂きました。 その結果、下水道局では、「経営計画2010」に基づき、石神井川流域の田柄川幹線流域において、新たな下水道施設の検討を3ヵ年で進めるとし、さらには、昨年2月に公表された、「経営計画2013」において、「練馬区田柄・桜川地区」を、新たに浸水対策の重点地区に位置づけ、平成25年度から平成27年度の3ヵ年の間に、まずは、城北公園から北町中学校までの、「第二田柄川幹線」の整備に着手すると伺っておりますが、進捗状況及び、工事のスケジュールはどうなっておりますでしょうか。 【⇒5-①答弁】 26年8月に工事に着手し、城北公園から北町中学校までを平成28年度末までに終え、残りの区間については、平成31年度に完了する。
-

上野ひろみ 一般質問(要旨)その1 2015年 1月 23日
定例会
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2018-11-7
<区の広報について> 【質問-①】 全庁を挙げての「戦略的な広報活動」が重要であると、私は思いますが、区長のご見解をお聞かせ下さい。さらに、今年度予算に計上されております、全国自治体初となるコマーシャル作成の進捗状況はいかがでしょうか。このCMの中に、新ビジョンを織り交ぜながら、練馬の魅力を区内外にお示しする最高の媒体となるよう期待をしております。 【⇒1-①答弁(区長)】 広報について、情報はすべて公開し、開かれた区政を実現することを目指している。また、組織体制については、様々な広報媒体を活用したPRをさらに展開するため、組織体制は、当面、区長室を中心に進める。 さらに、広報キャンペーンについては、映像や大判ポスターを活用したこれまでにない手法での広報展開を検討する。 【質問1-②】 「ねりまプロモーション係」を大いに活かして頂き、相談、あるいは連携し、「練馬ブランド」の更なる向上につながるように要望致しましたが、1年半が過ぎた今現在、どの様な状況でしょうか。その成果や課題があればお聞かせ下さい。また、民間採用(広報の専門家)の係長の任期延長はいかがお考えでしょうか。 【⇒1-②答弁】 マスコミ対応や印刷物のデザイン等の研修を実施し、職員の情報発信力を強化している。今後は、これまでの成果を基盤として、係の体制についても任期の延長も含め対応を検討する。 <教育について> 【質問2-①】 平成28年度から三学期制に移行することを、この度、決断して頂きましたが、今後の取り組みやスケジュール、また、三学期制に戻した場合、授業時間数がどのように変化するのか、想定をお聞かせ下さい。 【⇒-①答弁(教育長)】 平成28年度から、これまでの二学期制の成果を生かし、新たな三学期制に移行する。小学校で、数時間、中学校では、10時間程度減少するものと考えている。 【質問2-②】 これまで、我が会派は月2回の土曜日授業を要望して参りましたが、現在どのような検討状況にあるのか、また今後、土曜日授業を拡大するお考えはあるのか、お聞かせ下さい。 【⇒2-②答弁(教育長)】 今後も国や都の動向を注視しながら、必要に応じて回数の在り方について検討する。 【質問2-③】 小中一貫教育について、教育委員会としては、これまで、どの様な検証を行い、評価をされているのでしょうか、お聞かせ下さい。また、今後の小中一貫教育校の展開について、どのようにお考えか、「第二次学校適正配置」の検討状況と合わせて、具体的にお聞かせ下さい。 【⇒-③答弁(教育長)】 小中一貫校教育部会において検証作業を進めているが、異学年間の人間関係の深まりなど、様々な成果が生まれているととらえている。 また、今後の展開については、国の中央教育審議会でも制度化等の検討が進められており、今後は、国の動向を注視しながら、小中一貫校を展開する。 【質問2-④】 学校選択制について、教育委員会としても検証を行い、ある一定の方向性が見えてきているのではないかと推察しますが、適正配置との関わりの中で、今後どの様にお考えかお聞かせ下さい。 【⇒2-④答弁(教育長)】 中学校選択制度について、今後、課題の改善を図りながら、継続していくとの意見がまとめられた。また、区立学校の適正配置については、引き続き個別の検討を積み重ね、新たな小中一貫校の可能性も探りながら、検討する。 平成年第四回練馬区議会定例会 上野ひろみ 一般質問(要旨)その2はこちら://--////練馬区議会自民党 上野 ひろみ://-
-

第2回定例会 一般質問③ 2013年 6月 11日
定例会
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2018-10-10
【質問①】「少子高齢化による人口減少」、二つ目に「建物の老朽化による建て替え問題」、三つ目には「建て替え時の住民および関係権利者による、土地や建物の使い方」についてであります。 そこで、いくつかお伺い致します。区としてこれら難題・課題にどう取り組んでいくおつもりなのか、まずお聞かせ下さい。 また、区はこの度、建築基準法第86条のもとづく、「一団地認定」にそなえ、認定区域において、建築物の現況調査に取り組まれております。このことは、将来の「光が丘」を、更に「魅力的なまち」として行くための、極めて重要なきっかけになると認識しておりますが、この調査の目的と内容について、お聞かせ下さい。 また、調査を実施するにあたっては、関係事業者や権利者の理解と協力が不可欠であると考えます。充分な理解が得られるよう、適切な説明を行い、関係事業者が中心となって調査を実施し、調査に協力するにあたって、住民に大きな負担が生じないよう、最大限に努力して頂くことを要望致しますが、いかがでしょうか。区のご所見をお聞かせ下さい。 【答弁①】現況調査の目的は、社会状況の変化や光が丘地区の住民の意向を反映したまちづくりを具体的に前進させる取り組みである。また、住民負担については、事業者と区が負担する方向で、調整する。 【質問②】「まだ20年、30年先だから」と考えていては、このまちは、やがてゴーストタウンに変貌してしまうのではなかと、私は大変危惧しております。やはり行政がある程度リードし、住民や関係権利者はもとより、区全体に係わる課題、危機と捉え、早期に着手する必要があると考えますが、いかがでしょうか。 更には行政、区議会、区民間での協議を行い、「活気あふれるまち」になることはもちろんのこと、「付加価値のあるまち」例えば、「子育て世代に魅力のあるまち」を目指す。あるいは、「生活弱者にやさしいまち」を目指す。など、明確な将来像を描きながら、建て替え計画をまとめて頂くことを強く要望致しますが、いかがでしょうか。区のお考えをお聞かせ下さい。 【答弁②】将来の光が丘のまちの姿や、建替え計画などについては、支援を継続的に行い、発展させていく中で、話し合いの場を設け、創り上げていく。
-

第2回定例会一般質問② 2013年 6月 11日
定例会
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2018-10-10
【質問⑦】「練馬ブランド」について、昨年の第2回定例会の一般質問以来、私は練馬区における、区独自の、「シティプロモーション」が必要であると訴えて参りました。 そこで今年度から、我が会派の要望に応え、広聴広報課に、「ねりまプロモーション係」を新設され、民間から経験豊富な方を係長として採用されました。このことは、私はもちろん、会派としても大変評価していると同時に、大いに期待しているところであります。 地域の魅力を創造し、それを地域の内外へと広めることで『地域イメージをブランド化』し、魅力的なブランドに育て、観光客や転入者を増やすこと、住民に誇りや地元愛を根づかせることを目的とし、地元愛が高まれば、住民は町の発展に貢献しようとし、観光客に対するホスピタリティの精神も生まれるでしょう。そうなれば、一過性でなく持続的に発展していく環境ができるはずです。 そこでぜひとも、あらゆる部署が何かを区内外に発信する際には、新設された「ねりまプロモーション係」を大いに活かして頂き、相談、あるいは連携し、「練馬ブランド」の更なる向上につながるように要望致しますが、いかがでしょうか。また、今後の展望もお聞かせ下さい。 合わせて、以前から要望させて頂いております、組織改正を行い「広報課」を企画部内に設置し、区の更なる発展の為に、戦略的な広報活動に取り組んで頂くことを強く要望致しますが、区長のお考えはいかがでしょうか。お聞かせ下さい。 【答弁⑦(区長)】今年度中には、区の戦略的な広報施策に関する基本方針と広報計画を策定する予定であり、積極的にシティプロモーションを推進する。また、広報担当組織のあり方については、広報施策懇談会からの意見や他区の状況等も踏まえ、検討する。
-

第2回定例会 一般質問 ① 2013年 6月 11日
定例会
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2018-10-10
久しぶりに投稿させて頂きます。この度、「平成25年 練馬区議会 第2回定例会」において、一般質問を行いましたので、要旨を掲載させて頂きます。
-

(2)H24年 第2回定例会での一般質問 2012年 6月 14日
定例会
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2018-10-10
只今、開会されております「平成24年 第2回定例会」において、一般質問をさせて頂きました。今回で6度目となりますが、議場で発言するのは、毎回“緊張”致します。 今後もさらに、「始めよう、区民第一主義!」「やれば出来る!!」をモットーに、「温故知新」の精神で、一歩一歩着実に、日々勉強して参ります。更なる、ご指導・ご鞭撻宜しくお願い致します。 平成24年 第2回練馬区議会定例会 練馬区議会自民党 上野 ひろみ 一般質問(要旨)
-

(1)H24年 第2回定例会での一般質問 2012年 6月 14日
定例会
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2018-10-10
只今、開会されております「平成24年 第2回定例会」において、一般質問をさせて頂きました。今回で6度目となりますが、議場で発言するのは、毎回“緊張”致します。 今後もさらに、「始めよう、区民第一主義!」「やれば出来る!!」をモットーに、「温故知新」の精神で、一歩一歩着実に、日々勉強して参ります。 更なる、ご指導・ご鞭撻宜しくお願い致します。 平成24年 第2回練馬区議会定例会 練馬区議会自民党 上野 ひろみ 一般質問(要旨)
-

新年にあたり… 2012年 1月 4日
その他
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2018-10-10
新年を迎えるにあたり一言ご挨拶申し上げます。昨年も多くの方々に大変お世話になり、またお支え頂きましたこと、大変感謝申し上げます。 皆様におかれましては、それぞれお気持ちも新たに、新年をお迎えになられたことと存じます。 昨年は日本にとっては激動の一年となり、国民一人々々が色々と考えさせられる年(とし)となりました。私にとっても議員としての節目の年であり、期目の当選をさせて頂き、これまで以上に気を引き締め、日々、努力精進・邁進してまいる所存です。 そして、政策スローガンに「始めよう、区民第一主義。」を掲げ、自己主義になりがちな政治家が多く存在する中、政治本来の原点に立ち返り、さらなる行政改革・議会改革(議員定数削減等)にも取り組み、区民本意の政治の実現へ、皆さんと共に考え、共に学び、それぞれの分野で様々な経験・スキルを擁して、ネットワーク化を図る「協働・協治」を目指して参ります。 更には、私の好きな言葉の中に「温故知新」とういう言葉がありますが、「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る」、先人(先輩)方が築いて来たものや、考え、伝統を十分に研究・勉強し、新しい知識や見解を生み出していきたいと考えております。今後とも変わらぬご指導・ご鞭撻、そして、ご支援のほど宜しくお願い致します。
-

自分の意思を 投票という形で訴える責任!
編集室から
編集室
練馬区議ウェブ議員新聞から
2018-10-10
【 自分の意思を 投票という形で訴える責任! 】 東京都区に於ける練馬区長とは・・・ 区長とは区議会で決められたことに基づき、 実際に区の仕事を進めていく区のリーダーです。 練馬区議会議員とは・・・ 練馬区の自治体や、区民の声をひろいあげて、 練馬区議会を通し、可能な限り区政に反映させる役割です。 練馬区議会議員も練馬区長も、 ともに練馬区民の直接選挙により選ばれ、 それぞれ独立した権限を持ち、 相互に協力して区政を運営していきます。 練馬区民の皆さまは、地域・福祉・介護・子育てなど、 身近で困ったことが起こった時に どこに相談したらよいのか、 だれを尋ねたらよいのか、 とても悩まれることと思います。 練馬区役所の窓口に行かれて「管轄が違います」と、 幾つもの窓口をかけもちし、 たどり着くまでに、時間を費やされた経験のかたも少なくないことでしょう。 私自身、練馬の主婦である観点から申し上げますと、 区議会は、学校や幼稚園の組織にも似ています。 学校や幼稚園、によって、それぞれのカラーがあると思いますが、 我が子が健全に、学校・幼稚園生活をおくれるように、のかたが保護者の声を吸い上げてくれるのと同じように、 より良い練馬区を求めるのであれば、 練馬区議会議員さんに、ご自身の声を届けることです。 練馬区議の活動を区民に伝えるべき!と、 【練馬区議ウェブ議員新聞】へ記事の投稿をされている、一部の区議の方々は、 「何かあれば区民の皆さんに、いつでも相談に来ていただきたい。」と、口々に話されます。 とても些細な物事と感じても、 それが区政に参加していることに繋がるのです。 練馬区議会は、決して敷居が高いわけではありません。 練馬区で生活をしている、区民の一人ひとりが 「自分の意思を投票という形で訴える」 という、責任を持って 一票を投じる。 東日本巨大地震があり、日本の経済はもとより、 個人の意識も、大きく変わったかたも多いことと思います。 これからの練馬区には、何が必要なのか? 練馬区長選に於いて、練馬のリーダーを誰に託したいか? 身近な問題を、真摯に受け止めてもらえる練馬区議会議員は誰なのか? 練馬区民の皆さまが、ご自身の基準でキチンと判断をし、 しっかりと、見極めて、 投票していただきたいと思います。 ある議員は、「過去に、たった二票の差で、当選から外れました。 その時は本当に一票の重さを痛感しましたね」と、話されていました。 練馬区民、一人ひとりの皆さんに、一票の大切さを感じ取ってほしいと思います。 編集室(ち)
-

東北関東大震災~練馬区の対応について 2011年 3月 23日
安心・安全
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2018-10-9
~謹んで地震・津波による災害のお見舞い申し上げます~ この度の災害により、被害を受けられた皆様に対し心からお見舞い申し上げます。一日も早い復旧・復興と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。 今、被災地の皆さんは、度々起きる余震に眠れない日が続き、寒さに耐え不自由な生活を強いられている事と、心を痛めております。 「大丈夫ですよ。希望を持ってください。」の慰めの言葉さえ、むなしさを感じてしまうほどの惨状の中、赤ちゃんにミルクを、寒さに震えている子供たちに温かいスープを、壁により掛けた疲れた身体に毛布を、座り込んだその冷たい床に座布団だけでも…、そんな思いで、上野ひろみは被災地救援活動に協力し、日本中の人が、被災者の方たちに目を向け、助け合う気持ちで、元気を、希望を、与えてあげなければいけないとの思いで、活動して参ります。 先日、練馬・光が丘・石神井公園駅前にて、自民党練馬総支部が救援募金活動行いました。老若男女、多くの方々に募金して頂きました。ご協力ありがとうございました。 私も光が丘駅にて立たせて頂きましたが、特に若い方々がおこずかいの中から募金して下さる方が目立ちました。とても感動致しました。本当に皆さんありがとうございました。 また、区長に提案しました、閉校を使っての避難者の受け入れも実現する運びとなりました。 <練馬区の対応>・・・3月23日現在 ①避難者の受け入れについて 平成23年3月で閉校した小学校跡施設2ヵ所の教室に避難者を受け入れます。 ☆受け入れ施設 ()旧光が丘第二小学校(光が丘--) 月日(金)から ()旧光が丘第七小学校(光が丘--) 月日(金)から ※避難者の車を停められます。毛布・水等を提供予定。 ☆対 象 東北関東大震災の避難者 ☆期 間 原則として受け入れからカ月の予定 ②旧光が丘第二小学校体育館で救援物資を受け付けます ☆受付品目は【赤ちゃん用品】熱さまし用ジェル状冷却シート、紙おむつ、おしり拭き、ベビーローション、ベビーオイル【高齢者用品】大人用紙おむつ、介護用ウエットシート、介護食用とろみ剤【飲食関係】介護食、カップめん、缶詰(調理がいらないもの)、飲料水【生活用品】コンタクトレンズケア用品(洗浄液・ケース)、使い捨てカイロ、生理用品、紙コップ、ラップ、水用ポリタンク、割り箸、毛布、タオル、バスタオル、ボックスティッシュ、トイレットペーパー、ごみ袋、ブルーシート、ドラムコード等。(詳細一覧は練馬区のホームページをご参照下さい。) ※未使用・未開封のものをお持ち下さい。 (使用期限のある場合は期限内のもの) ※衣料品については受け付けておりません。 ☆受付場所 旧光が丘第二小学校体育館(光が丘--) ※車での来場もできます。 ☆受付期間 月日(火)から、毎日午前時~午後時 (当面月日(木)まで) ③義援金を受け付けます 月日(木)まで下記の場所にて 募金箱の設置場所 光が丘・大泉区民事務所、各出張所、練馬文化センター 石神井庁舎・区役所1階案内 以上、詳細は区のホームページをご覧頂くか、下記専用ダイヤルにお問い合せ下さい。 東北関東大震災 練馬区専用ダイヤル☎-- 毎日午前:~午後:自民党でも救援募金を受け付けております。 振 込 銀行名 ゆうちょ銀行 店番019 口 座 (当座)00170-1-496731 口座名義 自民党東日本巨大地震救援募金口座
-

いよいよ、スタート!! 2011年 2月 2日
その他
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2018-10-9
2月4日から開会予定の、平成23年 第1回定例会に先立ち、昨日より我が会派(自民党)による勉強会がスタートしました。 定例会中に開催されます、「予算特別委員会(来年度予算の審議)」において、質問する内容を、予算説明書等の資料を基に、15名の自民党議員で議論・協議し、決めて参ります。 質問内容が決まると、各々が、区の理事者(課長以上)からのヒアリングや、他区や他自治体の現状等、あるいは各種団体、各地域の要望事項を調査し、予算特別委員会の中で、区長や関係所管に対し質問し、要望や指摘をして参ります。 上野 博巳
-

平成23年 年頭のご挨拶 2011年 1月 11日
その他
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2018-10-9
明けましておめでとうございます。旧年中は多くの方に大変世話になりましたこと、この場をお借りして御礼申し上げます。今年も宜しくお願い申し上げます。 さて、月日の経つのは早いもので、昨日成人式も終わり、練馬区でも恒例の豊島園での「成人の集い」が開催され、約人が成人の仲間入りをされました。「おめでとうございました。」 そして、今日は鏡開きであります。地元の神社でも古いお札や松などを燃やす行事「どんど焼き」が行われております。寒い中、氏子の皆さんお疲れ様でございます。 今年は我々議員にとっては、節目の年であります。私ごとですが、今月の日に歳になり、年男(卯)でもあります。 初当選以来、いろいろな方々にご指導頂き、培ってきたものを無駄にすることなく、心新たに、誠心誠意尽くして参ります。 また、政策スローガンに「始めよう、区民第一主義。」を新たに掲げ、自己主義になりがちな政治家が多く存在する中、政治本来の原点に立ち返り、さらなる行政改革・議会改革にも取り組み、区民本意の政治の実現へ、皆さんと共に考え、共に学び、それぞれの分野で様々な経験・スキルを擁して、ネットワーク化を図る「協働・協治」を目指して参ります。更には、私の好きな言葉の中に「温故知新」とういう言葉がありますが、「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る」、先人(先輩)方が築いて来たものや、考え、伝統を十分に研究・勉強し、新しい知識や見解を生み出していきたいと考えております。今後とも変わらぬご指導・ご鞭撻、そして、ご支援のほど宜しくお願い致します。 上野 ひろみ
-
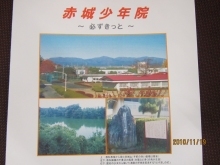
「赤城少年院」視察 2010年 11月 19日
その他
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2018-10-9
初めて記事を投稿させて頂きます。上野ひろみでございます。今回は先日行って参りました、「練馬区青少年育成第七地区委員会」の委員研修の報告をさせて頂きます。 まず「青少年育成地区委員会」とは、次代を担う青少年の健全育成と、青少年をめぐる社会環境の浄化を目的に、区内の出張所を単位に、青少年育成地区委員会が組織されています。現在、約千人の方々が委員として、地域で活動されています。青少年育成地区委員会では、毎年、青少年問題協議会の具申を受け、区が制定している「青少年育成活動方針」の重点目標を達成するため、地域で様々な事業の実施や青少年健全育成の啓発活動、防犯活動、不健全図書自販機等実態調査などを行っています。 また、区では青少年育成地区委員会活動の充実を図り、かつ円滑に行われるよう、各地区に青少年育成地区委員会事務局を設置しています。 という説明が、区のホームページにも掲載されております。 ちなみに私たち区議会議員は、各居住の地区において顧問というお役を頂いております。 そして、年間を通して、各地区において様々な事業を行っております。私の第七地区(田柄・北町西)では、「自転車安全教室」、「水泳教室」、「キャンプ・ハイキング・BBQ」、「ゴルフ教室」、「キャッチバレー大会」、「地域清掃・管内パトロール」などの事業を通し、青少年の健全育成に努めおります。
-

上野ひろみ議員 インタビュー 2010年 11月 1日
インタビュー
編集室
練馬区議ウェブ議員新聞から
2018-10-9
田柄側緑道は前回整備されてからすでに30年以上経ちました。老朽化が激しく、不備なところが出ている現状ですので、早急に再整備の必要があります。 「昔は川が流れていた」という面影も残しつつ、整備していきたいと思っています。しかし、人が通るのには狭い場所があったり、一部では下水が溢れている所もある為、治水対策も含んだ再整備を訴えていますがなかなか難しいのが現状です。それでも訴えの成果か、来年度くらいの見通しがようやく立ちました。