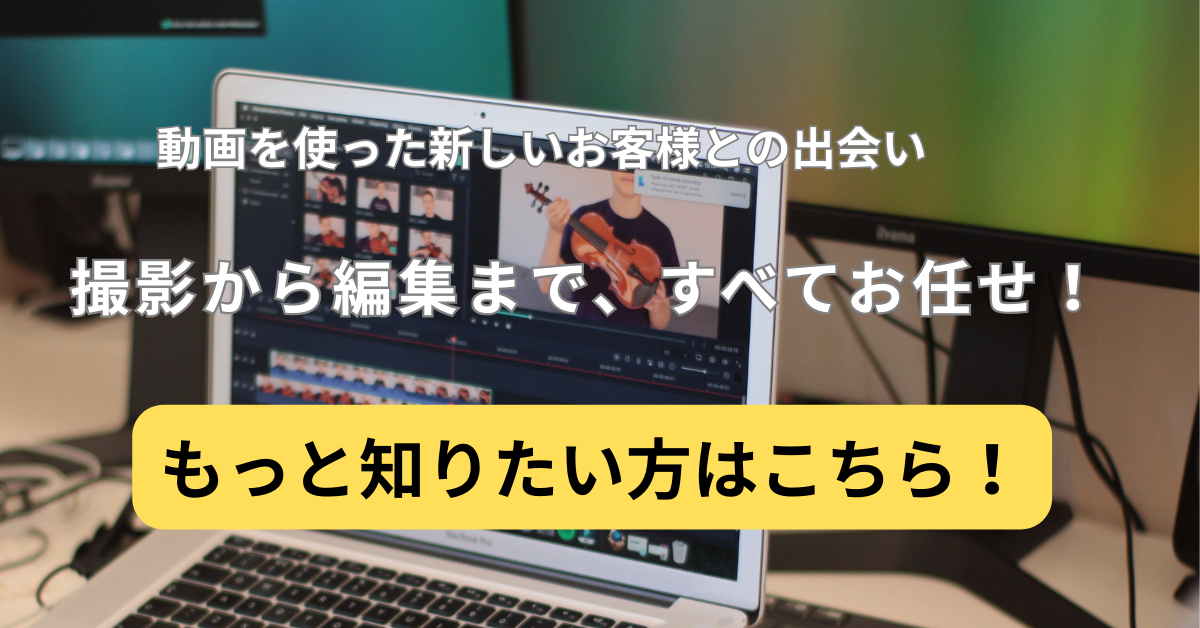練馬区のウェブ議員新聞から
- すべて
- 練馬区議ウェブ議員新聞から
-

なぜ練馬区は病床数が少ないか?聞いてみた
インタビュー
編集室
練馬区議ウェブ議員新聞から
2023-11-9
2023年9月、議員突撃インタビュー第二回を敢行しました。 編集長の私、実は二年ほど前に救急搬送されたことがあるのですが、その時は「練馬区の病院ではなく隣の板橋区か杉並区の病院に搬送します」と言われ、結果的に板橋中央病院に搬送されました。 なぜ練馬区内の病院ではなく板橋区の病院に搬送されたのか?いつも疑問に思っていたので、保健福祉委員会の副委員長でもあり、医療・高齢者等特別委員会でもある川澄議員に伺ってみました。 **************************** なぜ練馬区外の病院に搬送されることがあるのでしょうか? 〇かわすみ議員 練馬区は23区内でも病院の数、病床数が極端に足りません。 加えて、練馬区には三次救急医療機関という高度救急病院がなかったのです。 私が国会議員の秘書をしていた時から、「練馬区の病院ではなく、板橋区や三鷹市の病院に搬送されるので困っている、何とか練馬区の病院にならないか」という相談が多くなっていました。 この病院問題が大きくなっていることに、何とかしなくてはという思いで、区議会議員に立候補しました。以来、ライフワークとして練馬区の地域医療や搬送される病院の問題と病床数を増やすことを訴えています。 ようやく今年(令和5年)の4月に、順天堂大学練馬病院が三次救急病院に格上げされましたので、搬送の問題は少しは解消されるでしょうが・・・。
-

なぜ練馬区は23区中一番熱いのか?聞いてみた
インタビュー
編集室
練馬区議ウェブ議員新聞から
2023-9-8
2023年8月某日、上野議員に突撃インタビューを敢行しました。 猛暑続きの練馬。そういえばニュースなどで都内の猛暑が話題になると、決まって練馬区では・・・といった報道が流れることが多々あります。練馬区は23区の中でもとりわけ気温が高くなりやすいようですが、なぜなのだろうとの素朴な疑問を上野議員に質問してみました。 上野議員 「一般的には、東京の副都心の高層ビル群のオフィス機器や室外機などから出る熱で温められた空気が、 ちょうど太平洋からくる海風(南風)が内陸に向かって吹いてくることにより、練馬区の方に流れてくるのが原因の一つと言われているようです。そのほか、アスファルトが熱を持つことでヒートアイランド現象も原因の一つのようですね。」 気象庁のアメダスの観測地が石神井にあることも理由の一つかもしれませんが、練馬区は比較的、新宿などのビル群からくる排出熱による影響を受けやすい方角にあるらしいのです。そういえば、午後になると、「光化学スモッグ警報が発令しました」との公共アナウンスを耳にすることもあります。ゆっくりとしたアナウンスの声が流れると猛暑の熱気と相まって怖く感じてしまうことも。 上野議員は練馬生まれの練馬育ち。生粋の練馬っ子です。昔の練馬区もこんなに暑かったのですか?と伺ってみました。 「はい。私は練馬区に生まれ育って48年です。昔は31度~32度だったものが、今は35度が普通になっていますよね。練馬区は都内でも比較的緑の多い地域ですが、それでも、私が子供のころはもっと木々も農地も多かったですね。良くカブトムシやクワガタを捕ったりしましたが、今は屋敷林も減ってしまっています。」 なるほど。緑地の現象も練馬の猛暑の後押しをしているのだそう。
-

令和5年度の練馬区議会議長・副議長が決まりました
議会情報
編集室
練馬区議ウェブ議員新聞から
2023-6-14
練馬区議会第二回定例会では、毎年、新年度の議会議長及び副議長の選挙が行われます。 令和5年度の練馬区議会議長(第代)には、田中よしゆき議員が選出されました。 令和5年度の練馬区議会副議長(第代)には、酒井妙子議員が選出されました。 田中よしゆき議員(練馬区議会自由民主党)://--///酒井妙子議員(練馬区議会公明党)://--///
-

練馬区議会第二回定例会
議会情報
編集室
練馬区議ウェブ議員新聞から
2023-6-14
練馬区議会の令和年第二回定例会は、月日(月)から月日(火)まで開催の予定です。 一般質問は月日日日の日間です。 第期練馬区議会が発足されて初めての定例会です。 令和年第二回定例会の一般質問を傍聴に行きませんか? 議会の日程(月) ://////
-

区のお金の使い道 令和3年度決算より
その他
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2023-1-2
区のお金の使い道 令和年度決算より 昨年の第3回定例会において、令和3年度(2021年度)決算特別委員会が開かれ、賛成多数で認定されました。 令和3年度の一般会計は、歳入決算額が3173 億1790万円、歳出決算額が3066億5067万円で一人につき万円を交付した特別定額給付金事業などがあった年度と比べて、歳入は11%、歳出は、12%の減となりました。 【練馬光が丘病院跡移設における医療・介護の複合施設の整備】 昨年10月11日に練馬光が丘病院が移転し新たな病院が開院しました。(前回レポート掲載) その後の跡施設を活用し、地域医療包括ケア病棟および医療病棟を有する157床の病院を含む医療・介護の複合施設に生まれ変わり、令和年月の開設を目指します! 練馬区議会議員 上野ひろみ 公式サイト ://-/
-

上野ひろみ 練馬区議会議員
その他
上野 ひろみ
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党
2023-1-1
新年を迎えるにあたり一言ご挨拶申し上げます。 昨年も多くの方々に大変お世話になり、またお支え頂きましたことに感謝申し上げます。 令和4年も、何をやるにも新型コロナウイルス感染症に右往左往される一年となり、 私たちの生活は様々な場面で我慢を強いられることが多く、 精神的にも肉体的にも大変厳しい年であったと感じている方が多くおられる事と思います。 しかしながら少しずつですが、イベントや行事も開催され、旅行者も増え、まちの活気が戻りつつあります。 がしかし、まだまだ油断はできません。 皆様におかれては、引き続き「3密(密閉・密集・密接)の回避」、「マスクの着用・うがい手洗い・換気の徹底」等を行い、良い一年をお迎え下さい。 本年もどうぞ宜しくお願い致します。 さて先月9日に、「練馬区議会第4回定例会」も無事に閉会しました。 今後も地域の皆様のご要望に沿えるよう、無駄の無い区政を目指し、努力精進して参ります。 引き続き、「地元・ふるさと田柄・練馬区」の発展のため、 「平和台駅環八地下通路・エレベータの早期設置‼」、 「田柄川緑道の再整備!」、 「教育振興・子育て支援」、 「都市農業振興・農地保全」、 「スポーツ振興」、 「区の広報」、等々を中心とした、あらゆる施策の実現に向けて、前へ進めて参ります!! そして、区民の皆様を第一に考え、政策スローガンを「進めよう! 区民第一主義。」と掲げ、 自己主義になりがちな政治家が多く存在する中、 政治本来の原点に立ち返り、さらなる行政改革・議会改革にも取り組み、 区民本位の政治の実現へ、皆さんと共に考え、共に学び、 それぞれの分野で様々な経験・スキルを擁して、ネットワーク化を図る「協働・協治」を目指して参ります。 私の好きな言葉の中に「温故知新」とういう言葉がありますが、 「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る」、 先人(先輩)方が築いて来たものや、考え、 伝統を十分に研究・勉強し、新しい知識や見解を生み出していきたいと考えております。 今後とも変わらぬご指導・ご鞭撻、そして、ご支援のほど宜しくお願い致します。 練馬区議会議員 上野ひろみ 公式サイト ://-/
-
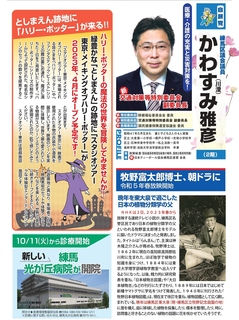
牧野富太郎博士、朝ドラに 令和5年春放映開始
その他
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2022-12-30
牧野富太郎博士、朝ドラに! 令和年春放映開始 NHKは2日、2023年春から放映する連続テレビ小説が、練馬区名誉区民であり日本の植物分類学の父といわれる牧野富太郎博士をモデルに描いたドラマに決まったと発表しました。 タイトルは「らんまん」で、主演は神木隆之介さんが務める。 牧野博士は、1862年に現在の高知県高岡郡佐川町に生まれた。 ほぼ独学で植物の知識を身につけ、1884年には東京大学理学部植物学教室へ出入りするようになった。以後、精力的に研究発表を重ね、『日本植物志図篇』や『大日本植物志』などの刊行にたずさわり、1889年には日本ではじめて新種ヤマトグサに学名をつけて発表した。1940年に刊行された『牧野日本植物図鑑』は、現在まで改訂を重ね、植物図鑑として広く親しまれている。晩年は練馬区東大泉(現・練馬区立牧野記念庭園の地)に居を構え、庭に移植した植物を採集したり、標本を整理したり、時に、訪問客と尽きることのない植物の話題に花を咲かせていたそうです。
-

かわすみ雅彦練馬区議 一般質問
定例会
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2022-12-6
一般質問(要旨)会派を代表して質問 【西武新宿線の立体化について】 かわすみ雅彦 質問① 地域住民と協働で、連続立体交差事業にあわせた積極的なまちづくりの検討・推進を。 また上井草駅周辺のまちづくりの今後の取組みは。 答弁① 事業の進捗状況など、地域住民に適宜 伝えながら、取組を推進していく。上井草駅周辺 は杉並区と連携を取りながら、まちづくりを進 めていく。 かわすみ雅彦 質問② 野方駅から井荻駅の都市計画の進捗状況は。 答弁② 都が構造形式や施行方法の検討を行っていると聞いている。今後も都や沿線区の取組 状況の把握に努めていく。 かわすみ雅彦 質問③ 各路線との相互直通運転を関係機関に働きかけを。 答弁③ 相互直通運転については、具体的な計画はないが、西武新宿線と新宿駅を結ぶ地下通路の整備が予定されており、利便向上につながるものと期待している。 【地域医療および在宅医療について】 かわすみ雅彦 質問① 区内の病院配置状況を考慮しながら病床の確保に取り組みを。 答弁① 令和7年度には2800床を超え、約1000床の増床となる。 かわすみ雅彦 質問② 順天堂練馬病院の三次救急医療機関実現を。 答弁② 早期指定をめざす かわすみ雅彦練馬区議員プロフィールはこちら://--///かわすみ雅彦公式ホームページ:///
-

練馬区議会 第四回定例会 令和4年度
議会情報
編集室
練馬区議ウェブ議員新聞から
2022-12-5
月日(金)から月日(金)まで令和4年度 第四回定例会が開催されています。 尚、日程は変更になる場合があります。 新型コロナの感染防止のため、本会議場での傍聴、及び委員会の傍聴はお控えください。 ● 傍聴の際の諸注意 傍聴の際は、受付時の検温にご協力をお願いいたします。 発熱または体調不良時の傍聴はご遠慮願います。 マスクの着用、入室時の消毒・手洗いなど、感染防止対策をお願いいたします。 ******************************** 【第四回定例会一般質問の内容はこちら】:///////【第四回定例会の議案の詳細はこちら】:///////【委員会および本会議の日程】月の予定表://////月の予定表://////提出した意見書
-

石神井中学校の雨漏り問題について(要旨)
災害・防災対策
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2022-12-5
●かわすみ議員 決算書445ページ、中学校改修工事経費 億8、000万円余に関連して「石神井中学校」の雨漏りについて伺います。 先週(令和3年9月)私に石神井中学校の会長から、至急、学校の雨漏り現場を見てほしいという連絡がございまして、4階にある1クラスに案内されました。 保護者からは1日でバケツ2杯分の水が天井から漏れ落ちるとのことでした。 現在、石神井中学校は、1年生6クラス、2年生6クラス、3年生5クラス、計クラスで00名の生徒がかよっている。ひと教室の生徒さんは3階の「多目的室」を臨時教室として使用しております。 先ず、屋上の防水工事はいつ行ったのか? ●学校施設課長 平成年度に屋上防水 工事と外壁等 の改修工事を併せて行っております。平成年6月6日から同年月日まで工事を行いました。 ●かわすみ議員 その防水工事の経費は約1億2、600万円余で、かなり大きな額でありますが、屋上防水工事の保証期間は? ●学校施設課長 雨漏りの原因によっては 年年保証。外壁からであれば5年保証ということで、原因によって対応は分かれてまいります。 ●かわすみ議員 私も学校の屋上に上りまして、数か所の原因と思われる箇所を確認した。 仮に、原因が屋上ダクト部分の一部亀裂だとして、その施工業者が改修工事を行ったとする。工事終了後から2年後に、また同様の雨漏りが出たとしたら保証はされるのか? ●学校施設課長 申し訳ございません。現時点で明確なお答えはできません。 ●かわすみ議員 約5年前に1億2、600万円もかけて補修したにも関わらず、その後5年経過して雨漏りが発生した。それがまだ分からないというのは、どういうことか理解に苦しみます。その施工業者に、区はしっかりとチェック体制をとり、徹底的に調査をすべく強く要望する。 さて、この問題のもう一の課題は、対応が非常に遅い、とのことです。令和3年9月日に雨漏りが発生し今日で2週間以上経過しております。なぜこれほど時間がかかるのか? ●学校施設課長 今回は、生徒をはじめ、学校関係者の方に御不便をおかけし、事態を大変重く受け止めているところです。早急に原因を特定し、適切に対応してまいります。 ●かわすみ議員 2週間も放置していたということだが、本当に子どもたちが不憫だと思わないのか。私も含めて、これでは行政に対する不信感と憤りを感じざるを得ません。この件について課長でなく部長答弁を要求するが如何か? ●教育振興部長 私どもも、日頃から良好な教育環境を確保するために、日常点検と改修を進めておりますが、確かに、一方では老朽化が進んでいる状況があります。 学校施設の今後の改築の選定は「練馬区学校施設管理実施計画」に基づき、長寿命化の適否を判断した上で、御指摘の建築年数、また、避難拠点としての役割などを総合的に考慮して選定してまいりいと考えてございます。 【令和年決算特別委員会会議記録より抜粋】 写真 「前川あきお区長」に石神井中の雨漏り対策等の陳情 (約名の署名)をの皆様と共に直接手渡しました。 かわすみ雅彦議員プロフィール://--///
-

石神井公園駅南口西地区 市街地再開発事業に着手
まちづくり
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2022-12-5
1、市街地再開発事業の事業着手に向けた取組等を支援石神井公園駅南口西地区における市街地再開発事業および関連する都市計画については、2年月に都市計画決定しました。 組合設立認可に向けた事業計画の作成や、その後の権利変換計画の検討等を支援し、事業を促進します。 2、都市計画道路と南口商店街の街並み整備を推進補助号線については、再開発事業とあわせて富士街道から再開発事業区域の区間において、4年度の事業認可取得に向けて取り組みます。 南口商店街においては、無電柱化にあわせた「街並み整備計画」の策定に向けて、地域の皆様と検討を進めます。
-

練馬区議会 第三回定例会 令和4年度
議会情報
編集室
練馬区議ウェブ議員新聞から
2022-9-13
月日(水)から月日(金)まで令和4年度 第三回定例会が開催されています。 新型コロナの感染防止のため、本会議場での傍聴、及び委員会の傍聴はお控えください。 ● 傍聴の際の諸注意 傍聴の際は、受付時の検温にご協力をお願いいたします。 発熱または体調不良時の傍聴はご遠慮願います。 マスクの着用、入室時の消毒・手洗いなど、感染防止対策をお願いいたします。 ******************************** 【第三回定例会一般質問の内容はこちら】:///////【第三回定例会の議案の詳細はこちら】:///////【委員会および本会議の日程】 9月の予定表://////月の予定表://////【提出した意見書等】 「卑劣な暴力に屈せず、自由で公正な民主主義を堅持する決議」 令和年月日、演説中の安倍晋三元総理大臣が銃撃され、尊い命が奪われた。ここに改めて、御逝去を悼み、心から哀悼の意を表す。民主主義の根幹である選挙が行われている中で発生した卑劣な蛮行は断じて許すことはできない。言論及び政治活動の自由を守ることは民主主義の基本であり、暴力による実力行使は最も憎むべき行為である。 私たちはあらゆる暴力を根絶し、自由で公正な社会を未来につないでいく責務がある。よって、本区議会は、「あらゆる暴力の根絶」と「自由で開かれた民主主義の堅持」に力を尽くしていくことを誓う。以上、決議する。 令和年月日 練馬区議会 **********************************
-

令和4年度練馬区議会の新議長と副議長が決まりました
議会情報
編集室
練馬区議ウェブ議員新聞から
2022-6-9
練馬区議会6月の第二回定例会では、毎年、次年度の議会議長の選挙が行われます。 次年度の新しい議長(第74代)には、藤井たかし議員が、 そして副議長(第76代)には、柳沢よしみ議員が選出されました。 第74代議長に藤井たかし議員が選出 藤井 たかし議員のプロフィール://--///第76代副議長に柳沢 よしみ議員が選出 柳沢 よしみ議員のプロフィール://--///
-

練馬区の病院整備とその課題について
定例会
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2022-1-3
練馬区議会 第回定例会 1 今後の病床確保および病院整備について 団塊の世代の全てが後期高齢者となる令和7年に向けて、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的、継続的に提供される地域包括ケアシステムを確立しなければなりません。 そのためには、高度急性期・急性期から回復期・慢性期、在宅医療に至るまで、切れ目のない医療提供体制の整備が重要であります。 平成年には約床だった病床は、現在、計画している病院整備が全て完了する令和7年度には床を超え、約床の増となる。それに加えて、高度急性期・急性期の医療機能が拡充するとともに、区内4つの圏域全てに回復期リハリビテーション病床および地域包括ケア病床が配置され、超高齢社会において求められる、慢性期病床も増床となります。 病床の整備には制度上、様々な制約がある中で、これらの事業が着々と推し進めて参りました。 しかし、練馬区の人口万人当たりの一般・療養病床数は、区平均の約3分の1から約2分の1に改善されるものの、依然として区最低の状況であることには変わりがない。 このような状況を踏まえれば、引き続き、病床の確保に向けた取組に全力で邁進してまいります。 かわすみ雅彦 公式サイト :///
-

新しい議長と副議長が決まりました 2021年度
議会情報
編集室
練馬区議ウェブ議員新聞から
2021-6-17
練馬区議会6月の第二回定例会では、毎年、次年度の議会議長の選挙が行われます。 次年度の新しい議長(第3代)には、かしわざき強議員が、 そして副議長(第代)には、吉田ゆりこ議員が選出されました。 第73代議長にかしわざき強議員が選出 かしわざき強 議員のプロフィール://--///
-

石神井公園のまちづくり
まちづくり
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2021-6-15
石神井公園駅の南口は駅前は無電柱化済み。 おおとり神社通りを無電柱化します。
-

高野台の長命寺通り「まちづくり」
まちづくり
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2021-6-15
交通事故のゼロと、災害時に備えた「まちづくり」を実現! 写真は、高野台の長命寺通り 高野台の長命寺通りにリハビリ病院が建設中。 車、自転車、人の往来増を見込み、道幅を拡張しました。
-

令和元年第四回練馬区議会定例会 かわすみ雅彦一般質問(要旨)
まちづくり
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2021-3-25
令和元年第四回練馬区議会定例会 にて 練馬区議会自民党 かわすみ雅彦一般質問(要旨) <新型コロナ感染症対策について> 質問① 相談や検査等ついて区民に周知と感染予防に関する注意喚起を。 答弁⇒① 様々な媒体を活用して周知している。感染者が急増していることを受け、改めて周知が必要。 質問② PCR検査を積極的に実施し、感染者の早期発見を。 答弁⇒② 検査は濃厚接触者以外の施設利用者を含め、広く実施し感染者の早期発見に努める。 質問③ インフルエンザの年末年始への区の対策は。 答弁⇒③ 高齢者インフルエンザ予防接種を無料化した。引き続き、周知に努めていく。年末年始にも診療・検査が滞る事がないよう医師会、区内医療機関と協議を行っている。 質問④ ワクチンについての取組みは。 答弁⇒④ ワクチン接種の実施が具体化し次第、速やかに開始できるよう、医師会とも協議を進めていく。 質問⑤ 事業者への新たな特別貸付の実施を。区の所見は。 答弁⇒⑤ 融資を受けた事業者の返済負担額が軽減され、計画的な返済と新たな事業展開に繋がる借り換え可能な貸し付制度について検討。 質問⑥ ウィズコロナサポート事業の周知と活用を。区の考えは。 答弁⇒⑥ 経済団体などと連携して事業者への周知等に積極的に取り組み、本事業の活用を推進していく。 <外環工事について> 質問② 調布市の外環工事現場付近で発生した道路の陥没についての区の対応は。 答弁⇒② 国等の事業者に対し、十分な調査と早急に原因究明、区民および区に丁寧な周知や説明を行うことなどを要請。事業者に対し工事の安全、安心を期した上で、外環事業に取り組むよう求めていく。 <都市計画道路について> 質問① 整備の進捗状況は。 答弁⇒① 現在、都では9路線で事業を実施、用地測量など事業化に向けた準備を進めている。区は5路線で事業を実施、事業化に向けた準備を進めている。 質問② 未着手の都市計画道路についても、積極な整備を。 答弁⇒② 道路整備が遅れている練馬区が、東京全体のネットワークから取り残されることがないよう、積極的に都市計画道路の整備に取り組んでいく。 質問③ 補助132号線の通称名を公募により選ぶなど、区民が関心を持てるような親しみのあるものに。見解は。 答弁⇒③ 都市計画道路など整備により一定区間のネットワークが図られた際には、通称名の設定について検討していく。
-

災害に強いまちづくり 定例会一般質問より
まちづくり
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2020-12-14
<災害に強いまちづくりについて> 質問 防災まちづくり事業の狙いは。 答弁⇒木造住宅密集地域の改善のため、密集住宅市街地整備促進事業に取り組んできている。その他改善が必要な3地区を防災まちづくり推進地区に指定。アンケートでは、避難に関する際のルートや地域の危険な箇所等について貴意見があった。 今後とも、区民と防災上の課題を共有し、災害に強いまちづくりをすすめていく。 <外環工事について> 質問 調布市の外環工事現場付近で発生した道路の陥没についての区の対応は。 答弁⇒国等の事業者に対し、十分な調査と早急に原因究明、区民および区に丁寧な周知や説明を行うことなどを要請。事業者に対し工事の安全、安心を期した上で、外環事業に取り組むよう求めていく。 <都市計画道路について> 質問 ①整備の進捗状況は。 答弁⇒①現在、都では9路線で事業を実施、用地測量など事業化に向けた準備を進めている。区は5路線で事業を実施、事業化に向けた準備を進めている。 ②未着手の都市計画道路についても、積極な整備を。 答弁⇒②道路整備が遅れている練馬区が、東京全体のネットワークから取り残されることがないよう、積極的に都市計画道路の整備に取り組んでいく。 ③補助132号線の通称名を公募により選ぶなど、区民が関心を持てるような親しみのあるものに。見解は。 答弁⇒③都市計画道路など整備により一定区間のネットワークが図られた際には、通称名の設定について検討していく。 <長命寺通りについて> 質問 高野台新病院等により交通量の増加への対策を。 答弁⇒病院の建設事業にあわせて、当該部分の車道の拡幅や歩行者空間の確保を事業者と協議し安全対策に努めていく。 <毎年同様の質問。石神井公園駅のホームドア設置について> 質問 石神井公園駅のホームドア早期設置を。所見は。 答弁⇒引き続き西武鉄道に対して、早期設備を働きかけていく。 <西武新宿線について> 質問 ①西武新宿線連続立体交差計画等の説明会での区民からの意見と今後のスケジュールは。 答弁⇒①構造形式や、環境保全対策のほか、工事の完了時期などの事業スケジュール等について質問があった。今後、令和3年度の都市計画実施、令和4年度もしくは5年度の事業許可の取得を予定している。 ②連続立体交差事業に伴う「まちづくり」の重要性を沿線区市にアピールを。区の考えは。 答弁⇒②沿線区市の先頭にたってまちづくりを進めていくとともに、都と連携し、連続立体交差事業の早期実現化に向けて全力に取り組んでいく 令和元年第四回練馬区議会定例会 練馬区議会自民党 かわすみ 雅彦 一般質問(要旨)より
-

生活困窮者対策について 定例会一般質問より
定例会
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2020-12-14
生活困窮者対策についての 質問 ①住居確保給付金等の支給状況は。 答弁⇒①利用者の生活状況や生活上の困り事を把握するため、面談や電話調査を行っている。利用者のうち約2割は現在も主食活動中。3割は転職を希望している。 ②生活保護に至る前の自立支援策の強化を。区の所見は。 答弁⇒②生活困窮者の多様な就労ニーズにきめ細かく対応し、早期の生活再建につなげていく。 ③生活保護世帯の頻回受診対策と、健康管理は。 答弁⇒③同一傷病について、一か月で15日以上の通院を指導対象とする基準を設けた。基準に基づき、頻回受信者を抽出し、ケースワーカ―等から指導と個別の健診受信勧奨を行っている。引き続き、医療扶助費の適正支給に向け積極的に取り組んでいく。
-

新型コロナ対策について 定例会一般質問より
医療
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2020-12-14
令和元年第四回練馬区議会定例会 練馬区議会自民党 かわすみ 雅彦 一般質問(要旨) 新型コロナ感染症対策についての 質問 ①相談や検査等ついて区民に周知と感染予防に関する注意喚起を。 答弁⇒①様々な媒体を活用して周知している。感染者が急増していることを受け、改めて周知が必要。 ②PCR検査を積極的に実施し、感染者の早期発見を。 答弁⇒②検査は濃厚接触者以外の施設利用者を含め、広く実施し感染者の早期発見に努める。 ③インフルエンザの年末年始への区の対策は。 答弁⇒③高齢者インフルエンザ予防接種を無料化した。引き続き、周知に努めていく。年末年始にも診療・検査が滞る事がないよう医師会、区内医療機関と協議を行っている。 ④ワクチンについての取組みは。 答弁⇒④ワクチン接種の実施が具体化し次第、速やかに開始できるよう、医師会とも協議を進めていく。 ⑤事業者への新たな特別貸付の実施を。区の所見は。 答弁⇒⑤融資を受けた事業者の返済負担額が軽減され、計画的な返済と新たな事業展開に繋がる借り換え可能な貸し付制度について検討。 ⑥ウィズコロナサポート事業の周知と活用を。区の考えは。 答弁⇒⑥経済団体などと連携して事業者への周知等に積極的に取り組み、本事業の活用を推進していく。 令和元年第四回練馬区議会定例会 一般質問(要旨)練馬区議会自民党 かわすみ 雅彦
-

川澄まさひこ 一般質問より3 2018年 10月 3日
定例会
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2018-11-8
〇胃がん検診の取り組みについて伺います。 2016年のガンの部位別死亡数は、胃がんは男性では肺に次いで2番目に、女性は4番目になっております。 また、2013年の全国推計値では男女合わせて罹患数では最も多いものが胃ガンであります。胃がんも早期発見早期治療を行えば、治るガンとされていることは、既にご承知の通りです。 区では、今年度から50歳の方に限定して胃内視鏡検査を導入致しました。まず、現在の内視鏡検査の受診状況を教えてください。 また、胃エックス線検査ではバリウムを飲むことや検査で放射線を浴びるなどのデメリットがありますが、胃内視鏡検査はありません。 早急に内視鏡検査の対象者を50歳以上のすべての方に拡大すべきであります。今後の区の胃がん検診の在り方について、ご所見をお伺いします。 〇後期高齢者を対象とした歯科健診について伺います。 口腔機能は、ただ食べるだけでなく、コミュニケーションを行う上で重要な役割を果たしており、高齢者の健康に大きく影響を及ぼすことで近年、広く知られています。 厚生労働省の健康情報サイトでは、口腔機能の健康への影響について次のように説明しています。かみ砕いたり、飲み込む機能が低下すると、食べ物の種類が制限されるため、栄養の偏りやエネルギー不足となる。 結果的に、筋力や免疫力の低下が起こり、病気にかかりやすくなる。また、食事や会話に支障をきたすと、人との付き合いが億劫になり、家に閉じこもりがちになる。 その結果、身体的にも精神的にも活動が不活発になり、 高齢者では寝たきりや認知症の引き金にもなるとしています。 また、国立長寿医療研究センターの研究班の報告では、滑舌が悪くなる、わずかなむせや食べこぼし、噛めない食品が増えるなどの軽微な衰えのことを「口腔の機能が虚弱になる」という意味で「オーラルフレイル」と表現しています。 私は、「オーラルフレイル」へのいち早い気づきや、口腔ケアを適切に行うことによる健やかで自立した生活の確保のため、高齢者の口腔ケアの環境づくりが非常に重要だと考えています。 そこで、現在区が行っている歳から歳を対象とした成人歯科健診を、歳以上の後期高齢者まで対象を拡大するとともに、この健診の中で口腔機能の検査を併せて行うべきと考えますが、区の考えをお伺いします。
-

川澄まさひこ 一般質問より2 2018年 10月 3日
定例会
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2018-11-8
〇練馬区の避難拠点である区立小中学校の体育館の空調設備について伺います。 国会でも、災害時の避難所である全国の小中学校の体育館の空調設備を早急に設置すべき、との流れの中で、補正予算を組む動きが出てきました。 昨年、我が練馬区は、前川区長の英断によりまして、概ね10年かけて、これらを設置することとされました。 しかしながら、今年7、8月のゲリラ豪雨や西日本豪雨災害を筆頭に、全国の至る場所での水災害、土砂災害、或いは、東京23区でも猛暑日が12日間連続を記録し、埼玉県熊谷市や高知県四万十市では、観測史上初の摂氏41・1度を記録するなど、地球規模の異変による自然災害が頻繁に起こっております。 これらを、報道等で見るとき、発災時における避難拠点の役割が日を追うごとに、益々重要になってきていると考えます。 よって、以上の観点から、この計画の前倒しを行い、一日でも早く、対象の区内全ての体育館に空調設備が設置・完了されますよう、我が会派として強く要望を致しますが 区のご所見を伺います。 〇まちづくりについて伺います。 まず、下石神井に関する課題についてです。 西武新宿線、上井草駅周辺地域は、練馬区の都市計画マスタープランにおいて、区民の日常を支える生活拠点として位置づけられております。 駅周辺地域では、西武新宿線の踏切による交通渋滞や歩行者の安全対策、商業環境の向上などさまざまな課題を抱えているとともに、首都直下型地震の発生を想定した安全・安心なまちづくりも求めてられております。 そこで、生活拠点として整備するにあたり、地域の中心である商店街通りのハード面の整備が必要であると、以前から、申し上げてきたところです。 整備に向けた、現在の進捗状況をお教え下さい。 〇西武池袋線の石神井公園駅のタクシーの利用状況について質問致します。 ご承知の通り、駅の北側、中央側にはタクシー乗り場が整備されております。 ところがタクシーの待機台数が少なく、使い勝手が非常に悪い、との区民からの強い改善要望がでております。 一方、大泉学園駅北口や練馬駅のタクシー乗り場には、充分な待機台数があり、昼夜を問わずタクシーの利用がスムースに行われております。 そこで、石神井公園駅周辺についても更なる利便性の向上に取り組んでいただきたいと要望致しますが、区のご所見をお聞かせ下さい。 〇西武池袋線の駅ホームドア設置について伺います 西武鉄道ではホームドアを一日の乗降者数が10万人を超える駅に原則設置するとされております。 その基準を満たす練馬駅では、既に今年度、ホームドアの整備に着手致します。 その整備には1列、約3億円の費用がかかりますが、 区は一列当たり、その3分の1以内、6000万円以下で補助を実施することになっております。 1日の乗降者数が10万人に満たないものの、その数に概ね順ずる「石神井公園駅」や「大泉学園駅」などにも区民の安全対策のため、ホームドアの早期整備が必要であると考えますが区の見解を伺います。
-

川澄まさひこ 一般質問より 2018年 9月 19日
定例会
かわすみ 雅彦
練馬区議ウェブ議員新聞から
練馬区議会自由民主党 副幹事長
2018-11-8
私は、練馬区議会自由民主党を代表し、一般質問をさせていただきます。 各理事者の皆様の誠意ある回答をお願いいたします。 先ず、質問に入る前に、今年6月の大阪府北部を震源とする地震、また、平成30年北海道胆振(いぶり)東部地震、7月の台風の上陸による豪雨災害などにより、亡くなられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げる次第です。 さて今年は、大きな自然災害が相次ぐ年となってしまっております。そこで、初めに自然災害対策について伺います。 6月18日の大阪府北部を震源とする地震では、大阪市、高槻市などで最大震度6弱を観測致しました。7月29日時点の総務省 消防庁のまとめによると、死者5名、負傷者435名、全壊12棟を含む住家被害4万1千744棟の被害が発生しております。 我が練馬区にとりまして最も警戒すべき「都市直下型地震」であります。 また、「平成30年7月豪雨」は、台風7号や梅雨前線の影響により、西日本を中心に全国的に大きな被害をもたらしました。同様に8月3日時点の総務省消防庁のまとめによると、広島県での死者108名をはじめ、200名を超える死者が発生し、住家被害は延べ3万4千棟を超え、平成に入ってから最も被害の大きい水災害となりました。 申し上げるまでもなく、災害から区民の生命と財産を守ることは区の責務であります。今般の災害を受け、前川区長は、全庁を挙げて、区の災害対策の再点検を行うよう指示をされました。 区はこれまでも、大きな災害が発生した際に、それを教訓として、より実効性の高い災害対策を構築してきたと認識しております。今般の2つの災害の教訓をどのように捉え、今回の「災害対策の再点検」のなかで、どのように取り組んでいくのか、お考えを伺います。 次に、ハザードマップについて伺います。 区民が避難行動を起こすためには、住んでいる地域の災害リスクを区民一人ひとりが認識している必要があります。その一つの媒体としてハザードマップがあります。 去る8月27日には区内でもゲリラ豪雨による被害が発生し、私の地元である下石神井でも床上浸水・床下浸水の被害が報告されております。 こうした水災害を受け、浸水ハザードマップの重要性が改めて認識されております。これを広く区民に周知し、水災害に備えていただくことが肝要であることは申し上げるまでもありません。